1.能楽とは
能楽とは

『能楽』は能と狂言の総称です。この言葉は明治時代以降に使われ、定着します。古くは、『猿楽』または単に『能』と呼ばれていました。
能楽は室町時代に観阿弥・世阿弥により大成され、600年以上の歴史を持ちます。江戸時代に幕府が儀式楽として採用し、以来古典芸能の代表的存在となり、諸藩・庶民にも広がって、現在に至ります。
なお、能楽は、2008年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。
能
能は音楽(囃子)を伴う歌舞劇で、登場人物はセリフや心情を謡い舞います。また登場人物は神や鬼、人間の霊、動植物の精など多様であり、生きた人間でも老人や女性の役には能面を着用します。
素材は『源氏物語』や『平家物語』など有名な古典から、世間に流布する噂を取り入れたものや作者の創作まで多岐にわたります。話し言葉(会話文)と書き言葉(語りや和歌)を縦横に織り交ぜた文章は、音読するだけでも調子の変化を楽しめます。古語も「日本語」と実感できるでしょう。綴られた美しい言葉の中から、心に残るお気に入りのフレーズを見つけてみるのも面白いかもしれません。
狂言
狂言には、『本狂言』と『間狂言』があります。
本狂言は狂言師だけ(囃子が入ることもあります)で演じられ、多くは庶民の失敗話をユーモアたっぷりに描きます。
間狂言は能の登場人物として主役・脇役に随行したり、主役にまつわる由緒を語ったりするなど、進行上重要な役割を担います。
どちらも生きた人間の割合が大きく、そうでない場合(本狂言の動物や、間狂言の末社の神など)は狂言面を着用します。
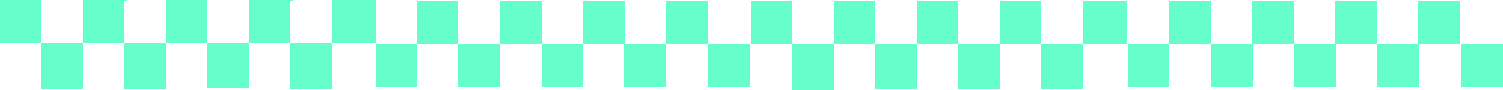
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています








更新日:2024年06月10日