6. 装束について
装束とは
色あざやかな生地に織り込まれ、華やかな文様で描かれた能の装束は、身にまとう演者のまわりの空気を変え、観客を能の世界にいざないます。
「装束」とは、かぶり物やかつらを含み、能を演じるときに演者が身につける衣装の総称です。身につける装束の種類は役ごとに決まっており、多くは現実の人々の衣服をもとにしながら、様式化・抽象化されています。そのため身分の低い人物、死者や鬼の役であっても、華美な装束を身につける場合もあります。
能が大成された室町時代初期の能装束は、簡素なものだったと考えられています。しかし、次第に中国から舶来した裂地や製織技法を使った、上質で華やかな装束が用いられるようになりました。現存する装束の中には、安土・桃山時代に製作されたものもあり、意匠や色遣いには豪華絢爛を好んだ時代性が反映されています。
さらに、江戸時代に入って能が武家の式楽になると、大名たちは手の込んだ装束をあつらえるようになります。同時期に西陣織の技術が発達したことも、装束の品質向上につながりました。当時の染織工芸の最高水準の技術や材料が用いられた装束は、美術工芸品としても高い価値を持つものと言えます。
色や文様からわかること
能装束は目で見て美しいだけではなく、その色遣いや文様の中には、物語と登場人物の情報が込められています。最小限の舞台装置で演じられる能では、これらの情報は作品を読み解く重要な鍵の一つです。例えば、秋の草花や風物を文様としてあしらうことで、物語が秋に展開されることを観客に示すことができます。
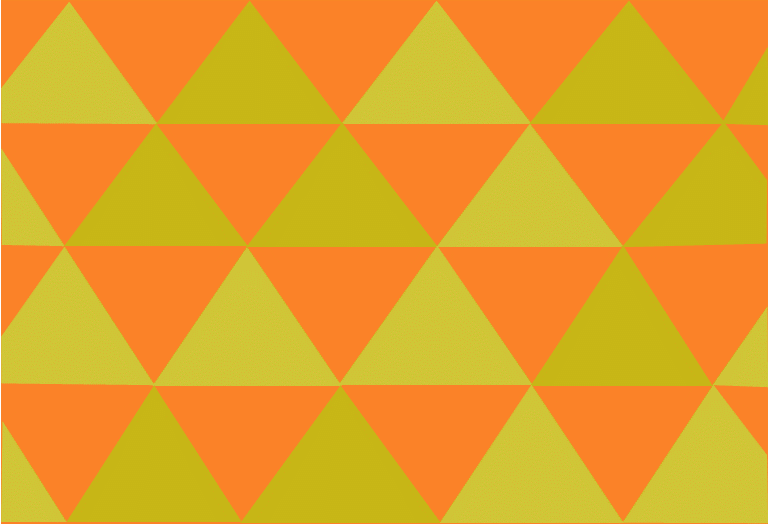
また、特定の模様によっても登場人物の特徴が表現されています。
代表的なものは、金箔で三角形を連ねた模様で、蛇の鱗を連想させるものです。この鱗箔を身に付けるのは『道成寺』『葵上』『鉄輪』といった演目のシテ(主人公)ですが、その正体が、実は蛇や鬼であることが暗示されているのです。
さらに、色遣いも登場人物の特徴と密接に関わっています。「紅入」という赤系の色を使用した装束は、主に若く美しい女性の役に用いられ、逆に「紅無」は赤系の色を使用せず、中年の女性の役に用いられる装束を指します。
用いる装束の種類は基本的に役柄によって決められていますが、その組み合わせは流派や演出によって変わります。また、具体的にどの装束を用いるかは、演者の裁量にゆだねられており、観客は同じ作品であっても、公演ごとに異なる雰囲気で楽しむことができます。このように、台本である謡本を基本としながら、装束や面の選択を通じて、物語世界が多層的に表現されていくところに、能の面白さがあるのではないでしょうか。
参考文献
・観世喜正、正田夏子(2004)『演目別にみる能装束:一歩進めて能鑑賞』淡交社
・横道萬里雄(1987)『岩波講座能・狂言4:能の構造と技法』岩波書店
・小山弘志(1989)『岩波講座能・狂言6:能鑑賞案内』岩波書店
・横道萬里雄(1992)『岩波講座能・狂言別巻:能楽図説』岩波書店
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています








更新日:2024年10月09日